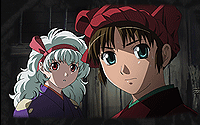|
2人の光景が消えた。
紅蘭麻は肩で呼吸をしていた。体も熱く火照っていて、まだ言葉を紡ぎ出す事が出来なかった。
体を冷まし、気持ちを落ち着かせるために、意識してゆっくりと呼吸をしていった。
やがて頭の働きもはっきりとして、冷静に分析が出来るようになってきた。
「では、ご先祖は、あの天女は……、この世を滅ぼすために、天から降りてきたというの!?」
紅蘭麻は自問するように言った。
どうせ応えてくれるのは、自分に流れる血の意志なのだから。
案の定、心に返事が返ってきた。紅蘭麻は動揺する心を抑えきれなかった。
「だが、最初の巫女は、かの地の男に情を通わせてしまい、緋王を召還せずこの世を去った」
意志の声は続く。しかし紅蘭麻は、未だわからない事を聞きたかった。
「それが本当だとすれば……、私の前に華虞夜という御方が既に……」
「………………」
紅蘭麻はその答えを待ったが、意志の声はそれには答えず、別の言葉を続けた。
「紅蘭麻よ、呀宇種の巫女よ。召還せし呀宇種の者は、この紋様を体のどこかに表している」
「天空より緋王を召還し、過去より与えられしその役目を果たすがいい……」
意志の声が強制的に話しを終わらせるように思える。
「お待ち下さい! 待って!!」
意志の声に必至に問いかけたが、紅蘭麻の意識はまた遠のいていった。
辺りは現世の夜に戻っていた。
聞こえる滝の音も、肌に感じる風も、儀式のために来た池のものだった。
紅蘭麻の意識もそれを理解したのだが、体の震えは止まらずに、岸辺にうずくまっていた。
「巫女様、お加減はいかがです?」
紅蘭麻の疲れ切った表情を、オガルが不安げに見つめていた。
体の火照りは感じられなかった。しかし今まで見てきたものは、はっきりと記憶に残っている。いや、正確には血の意志で思い出したものだろうが、特に天女の愁いのある瞳が、瞼の裏に焼きつくように残っていた。
「どれくらい……、時がたったのですか?」
紅蘭麻は恐る恐るオガルに訪ねた。
「へい、四半時もたっていませんな」
「……ん……」
オガルの言うとおり、月の浮かぶ位置はあまり変わっていなかった。ただ幾つかの薄い雲が、その前を流れただけのようだ。
「驚くのも無理はねえ。だが、これは宿命って奴だ。姫様はそれを受け入れるほか道はねえんだ。それはあっしも同じ事でしてね」
紅蘭麻が今まで見てきた事を知っているように、オガルが話し始めた。
「先に言ったとおり、天女は精霊を付き従える力ってやつを持ってやす。そして、このあっしがその精霊でさ」
オガルが小さいくせに胸を張って威張るように話している。
「月影に姫が生まれ出でた瞬間、あっしも世に現れやした。姫を守護するためにね。ま、言ってみりゃ、これがあっしの宿命ですな」
「オガル……」
「んがっ、なんでやすか?」
自己陶酔気味だったオガルは、慌てて紅蘭麻の言葉に耳を傾ける。
「私はどうしたらよいのでしょう? 私はただの十八になったばかりの娘。そのような大儀を背負う覚悟は……まして、この世を滅ぼす王など……」
紅蘭麻は今、自分の正直な気持ちを伝えた。
「姫がどうなさろうと、そりゃ姫の勝手でありやしょう。あっしには、なにも言うことはありやせん。姫を守るだけ、それだけがあっしに与えられた役目でやすから」
今いくら悩んだとて、すぐに答えは出ないだろう。紅蘭麻はその役目の重さに、絶えきられるのかとても不安だった。
「それより姫様。はやくお召し物を着ませんと……、その……、ケケケケ……」
オガルの笑い声に気付くと、紅蘭麻は自分が未だ一糸もまとっていない事に気付いた。
見るとオガルがそのひょうきんな顔をさらにゆがめて、ニタニタと笑って立っていた。
「……無礼者!」
紅蘭麻は素早く片手でオガルの頭を掴むと、思いっきり滝に向かって投げ込んだ。
「ケペーーーーーーーーッ!!!」
ドボーンという大きな音と、これまた大きなオガルの叫び声が、静寂な森と池に響き渡る。
これが自分を守護する精霊なのかと、紅蘭麻はとても不満に思えた。
急いで白衣を着込むと、そのままの勢いで池を後にした。
「ひっ、姫様ーーーっ! こりゃあんまりでやしょ~!!」
オガルのわめき叫ぶ声が聞こえる。さすが水の精霊、あれぐらいでは何ともないのだろう。
「ふふふ……」
そう思って笑うと、紅蘭麻は少しだけ気が楽になった。
それから数ヶ月後。
月影隆盛が突然病に倒れた。幾日も高熱が続き、しだいに体力も衰えていった。
紅蘭麻はあの後、儀式で起こった事の全てを話してはいなかった。いや話す事が出来なかった。
あのような交合の場面を赤裸々に語るのは、紅蘭麻にとってかなり抵抗があったことも事実であるが、なによりも、この世を滅ぼす王などということを、そう易々と口に出来るはずもない。まして病床に伏せる者に語るには、あまりにも酷であった。
それから数日が過ぎても隆盛の病は快方の兆しを見せず、家臣も八方手を尽くしてその治療法や名医と言われる者を捜し回っていた。
紅蘭麻はしばらく不安な日々を過ごしていたが、やがて宍戸幻斎(ししどげんさい)という男が典医として城中に出入りするようになった。
しかし紅蘭麻は、そのような状況になっても、この幻斎に全てを託す気にはなれなかった。不思議な事に、宍戸を誰が城中に連れてきたのか判然とせず、この者がどこの生まれなのか、ここに来る前はなにをしていたのかなど、彼の素性の詳細を知る者は領内に一人もいなかったからである。なにより、幻斎の自分を見つめる目に、尋常ならざる不気味さを感じていたのである。
だが彼の調合した薬のおかげで、一時的に隆盛の容態がよくなったことがあり、そのため、いつの間にか隆盛の典医として、月影家のお抱えとして出入りするようになっていた。
紅蘭麻は思った。
「今の父の症状なら、まだ他の医者や治療法を捜しても間に合う」
幸い都の方では、大陸に渡っていた者たちが引き上げてきている頃だ。医者として渡っていた者も、何か新しい技術を持ち帰った者もいるであろう。だとしたらこの病の治療法があるかもしれない。早い方がいい。
そこで今日にでもふれを出して、幻斎がこれ以上幅を利かせる前に取り決めをしてしまおうと考えたので、紅蘭麻は急ぎ隆盛に会いに行った。
「父上、お話があります」
紅蘭麻は父の返事を待たずに、その寝室の戸を開けた。彼女は意気込んでいたが、その時既に父の床の側には幻斎が座っていた。
「……幻斎!?」
紅蘭麻は少し動揺してしまった。しかしこの話を後にのばすのはよくない。
なるべく表情を変えないようにして部屋に入り、父を挟んで幻斎の向かいに座った。だが幻斎の姿を極力目に捉えないようにした。
隆盛は上体を起こして、茶のような物を飲んでいる。幻斎の調合した薬である事は間違いない。
「ああ、紅蘭麻か。よかった今日はいくらか気分がよくてな」
父はやつれていたとはいえ、そのやさしい眼差しと微笑みを愛しい娘に向けた。
「これはこれは紅蘭麻姫様。いつも凛々しいお姿で、ご健康にあらせまするな」
対照に幻斎の顔は、相変わらず不穏な面構えで気に入らなかった。
「幻斎の持ってくる、薬のおかげだ」
紅蘭麻は幻斎の挨拶を無視して、さっそく父に切り出した。
「それはようございました。それで父上、今、大陸から多くの者が帰ってきておりまする。その者たちの中には、新たな技術を得た者もおり……」
「おお、その事か」
「その事!?」
紅蘭麻が父の発した言葉に、自分の意見がそれだけで賛同を得たと思い、話しを続けようとした。
「それでは……」
だが父は紅蘭麻を制し、幻斎の方へ話しを向けた。
「今、同じような事を、幻斎から聞いていたところじゃ」
「幻斎が!?」
その方向を見なかったが、きっと幻斎はニンマリと笑って言っているのだろう。
「おそれながら殿の御病は、悪霊に取り憑かれているのかも知れませぬ」
(悪霊とは自分の事ではないのか……)
紅蘭麻は幻斎の事など、口にも出したくなかった。
それを知ってか知らずか、相槌を打たない紅蘭麻に対して、構わずに幻斎は続けた。
「先ほど姫様が申し上げたとおり、大陸での技術を会得して、同じような症状を治したという者がおりますれば、是非にと、殿にお目通りだけでもと思いまして」
「それは……!」
紅蘭麻はこれ以上、怪しい輩が増える事をよしとしなかったので、きつく反対しようとその事を聞き返した。だがそれに答えたのは、嫌っている男ではなく父の方だった。
「陰陽の術を会得した者だそうでな。幻斎が是非にと申すに、会うだけならと承諾した所じゃ」
「父上!!」
紅蘭麻はつい言葉を荒げてしまった。だが病人の前だと言う事、さらにそれが幻斎の前でと言う事に気付いて、瞬時に後悔した。
焦る気持ちを抑え、居住まいを正して、落ち着いた口調で言い直す。
「陰陽の類など、父上が日頃から嫌っていた者ではありませんか?」
「う~む、そうじゃが……、幻斎の申す事であるし」
「姫様。そういう者こそ、殿の病を治療するのに適しているのでございます」
「ふむ、今まで嫌っていた事柄なのでな、治療方法を知らなかったのかもしれんのじゃ」
(だめだ、父上はこの男に毒されている)
そう思った紅蘭麻だが、今は反論できるものを持ち合わせていなかった。
「さすが殿。実を申せば、よい事は早めにと思い、真に勝手ながら既に、これへ……」
幻斎は言うと、向こう隣の部屋へと合図を送った。
「はっ……」
人の動く気配がした。
(いつのまに……)
紅蘭麻は今まで、隣の部屋の事など気にしていなかったため、再び不安を感じていた。
(返事は、おなごのようであるが……)
隣部屋から続く戸が開き、尼僧姿の人物が現れる。
「お初にお目にかかります。幻斎さまの招きに応じて参りました、陀吉尼(だきに)と申すものでございます」
「おお、まさか尼僧とはの」
紅蘭麻は今度は驚きを隠す事が出来なかった。
(なんと妖しげな輩じゃ……、この様な者に病など治せるのか!?)
「ははは、驚かれましたか。しかし殿、これで病は治ったも同然でございまするぞ」
「ふふふ……、幻斎さま。まだ気が早うございます」
「おお、そうか。しかし間違いなく、殿のお体は回復いたしますぞ」
紅蘭麻の事を無視して、話を弾ませる幻斎と陀吉尼だった。
「陀吉尼とやら、頼りにするぞ」
父が幻斎につられて笑うのが、悔しくてしょうがなかった。
「どうか、ご安心召さますよう。ふふふ……」
すると陀吉尼がちらりと紅蘭麻を見て笑った。
「紅蘭麻姫。なにとぞ、よろしゅうに……」
その尼僧が丁寧に頭を下げるのを見ても、紅蘭麻にはとても安心できなかった。
それ以上に、父の病につけ込む幻斎のやり方に、激しい憤りを感じていた。
|